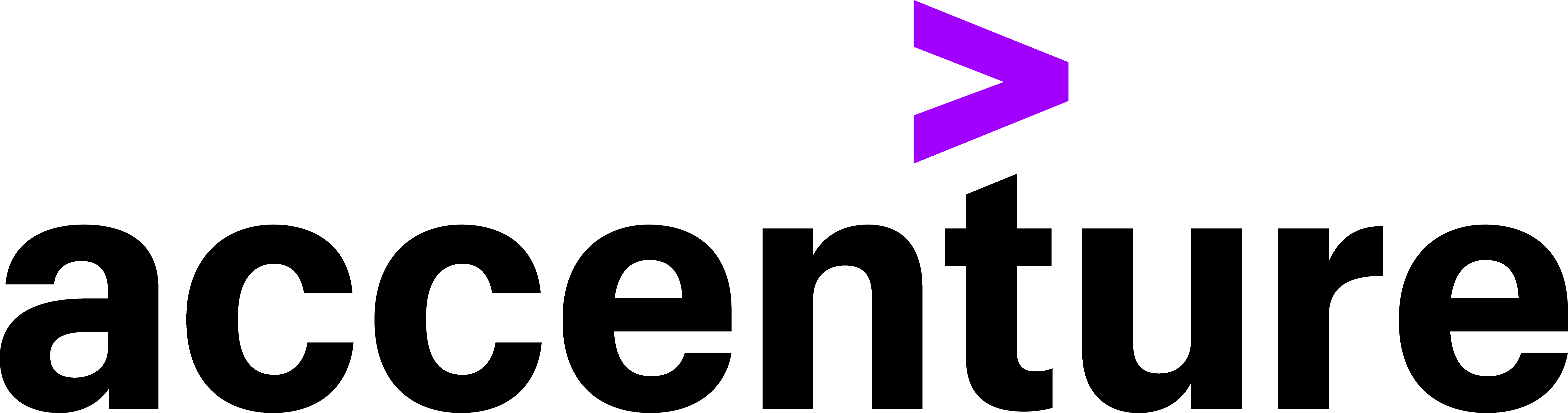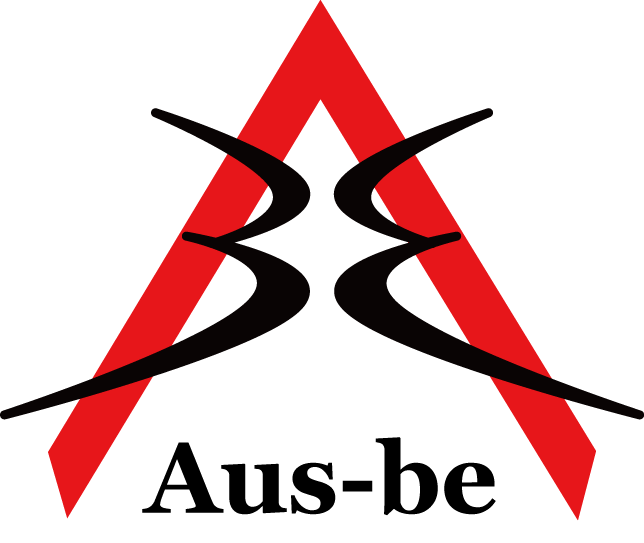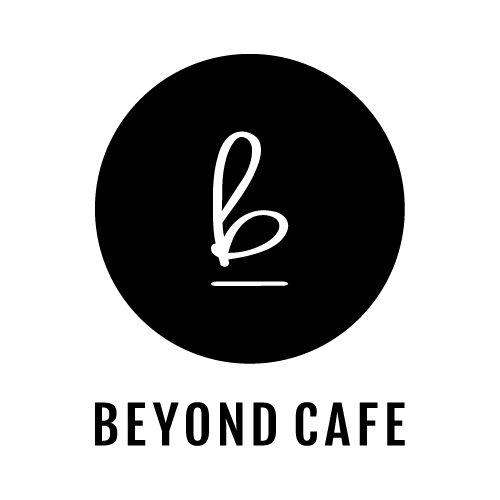Activating youth leadership since 1948.
アイセックは、第二次世界大戦後、1948年に7か国の7人の若者によってヨーロッパで設立されました。
「二度とこのような惨事は起こしてはならない」という想いから生まれたアイセックは、
今では100以上の国と地域に30000人以上のメンバーを持つNPO法人に成⻑し、
今も変わらず「平和で人々の可能性が最大限発揮された社会」を目指して活動しています。
MOVIE
Why We Do What We Do
私たちアイセックは、若者のリーダーシップこそがより良い明日への鍵であると考え、 若者が挑戦的な環境で実践的な経験をするための機会創出をしています。
About AIESEC
AIESEC(アイセック)は、海外インターンシップやオンラインの国際交流イベントなどを通じて
世界中の若者のリーダーシップを育むことを目指している非営利組織です。
1948年にヨーロッパで創設されて以来、
「平和で、人々の可能性が最大限発揮された社会」の実現を目指して活動しています。

100以上の国と地域
の支部

7000以上の
パートナー団体

年間30000件以上の
経験を提供
Our Programs


海外インターンシップ
日本の大学生を海外の企業、教育機関やNPO法人などへ送り出す海外インターンシップと、 海外の大学生を日本の企業様などに受け入れていただく海外インターンシップを運営しています。

global youth dialogue
海外の学生との様々な会話を通じて、世界をより広く、 自分をより深く知ることのできるオンラインイベントです。 海外の学生とペアを組み、 日替わりで設定される会話のトピックに基づいて自分や世界のことを話すことができます。
詳細はこちらOur Partners